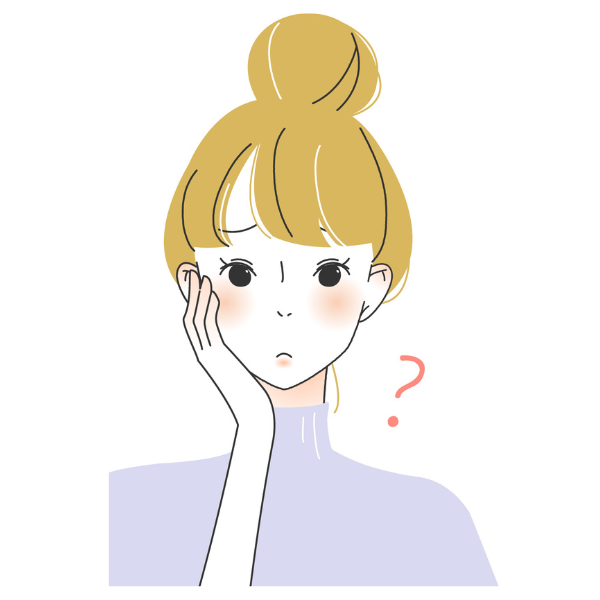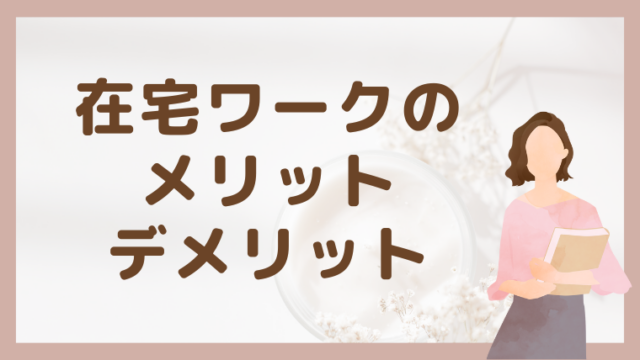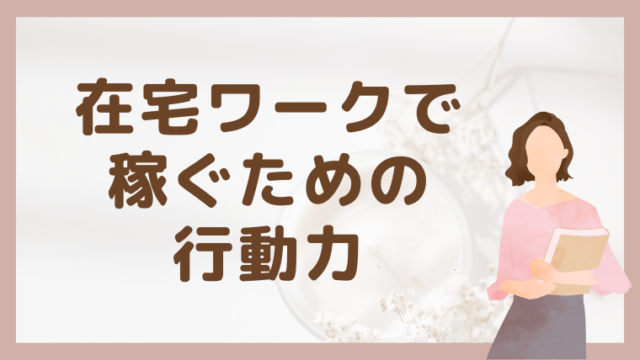読みやすい文章って、やっぱりセンスが必要よね…
実はこれ、私自身が最初にぶつかった壁でした。
書くたびに「まとまらない」「伝わらない」「読みにくい」と悩み続け、
やっぱり自分にはセンスがないのかも…と落ち込みました。
でも、ブログを添削をしていただく中で、
読みやすい文章には、「書き方」と「コツ」があることに気づきました。
センスではなく、技術だったんです。
私はこの「書き方」を知ってから、少しずつ書くのが楽しくなり、
読みやすくなった変化を感じるようになりました。
この記事では、私が今も実践している「読みやすい文章の書き方10の鉄則」と
その練習方法をお伝えします。
読みやすい文章とは?悪い例とよい例

読みやすい文章とは、
頭にスッと入ってきて、情景が自然と浮かび、読んでいてストレスを感じない文章のことです。
それではまず、悪い例とよい例を比べてみましょう。
私が在宅ワークを始めた理由は、子どもを長時間留守番させることが心配だったのと、通勤や昼休みの時間をもっと有効に使いたいと思ったからです。
毎日クタクタになって帰宅し、家事をこなすだけで精一杯。子どものことを後回しにしてしまう罪悪感もありました。今では、朝に子どもを送り出し、帰宅時間には「おかえり」と迎える余裕があります。
一文が長いと、読む前から「難しそう」「読むのが大変そう」と感じてしまい、
読むハードルが上がってしまいます。
内容は伝わっても、読む側は疲れてしまいます。
在宅ワークを始めてから、子どもとの時間がしっかり取れるようになりました。
なぜなら、通勤がなくなり、日中も自分のペースで動けるようになったからです。
今では、朝に子どもを送り出し、帰宅したときに「おかえり」と迎える余裕があります。
文章を短く区切り、ひとつひとつの要点をはっきり伝えるだけで、
ぐっと読みやすくなります。
このように、読みやすい文章にするためには、書き方にポイントがあります。
このあと、初心者でもすぐに実践できる「読みやすい文章の書き方の鉄則」を
具体的に紹介していきます!
読みやすい文章の書き方10の鉄則

文章の目的を明確にする
書く前に「この文章で何を伝えたいのか?」を決めましょう。
目的がないと、読者も「結局なにが言いたいの?」となってしまいます。
1記事1メッセージを意識して書きましょう。
読者ターゲットを意識する
誰に向けて書くかを具体的に決めると、内容にも一貫性が出ます。
みんなに読んでもらえるように書きました。
子どもとの時間も大切にしたい主婦に、在宅ワークの始め方を書きました。
PREPの型を使う
PREP=結論→理由→具体例→結論 の順で書く型です。
伝えたいことが明確になり、説得力が出ます。
毎日献立を考えるのってすごく大変ですよね。
私も以前はすごく悩んでいました。
月曜は魚、火曜は肉、水曜は麺類みたいに決めておくといいよって友達が言ってたので、私もやってみたら、けっこう楽になった気がします。
最近は、買い物もなんとなくスムーズになって、時間が有効に使えているような気がしています。
結論:私は、1週間のメニューの大枠をあらかじめ決めています。
理由:そのほうが、メニューを考える手間が減り、買い物もスムーズに済むからです。
具体例:たとえば、月曜と木曜は魚料理、火曜と金曜は肉料理、水曜は麺類、土日は少し手の込んだメニューにしています。
結論:あらかじめ大枠を決めておくだけで、献立に悩む時間が減って、家事の時短にもつながります。
一文を短くする(60文字以内)
文が長いだけで読む気がなくなり、見にくいので、一文は短くします。
なるべく省ける文字や言い回し、接続語を減らして短く。
一文60文字以内に短くと言われても、どのくらいの長さかわからないと思いますので、
この文の長さを目安にしてみてください。(59文字になります)
私は昨日買い物に行ったら友達に会って、最近オープンしたスーパーの話を聞いたので、早速行ってみたらセールをやっていて、野菜を安く買いました。
私は昨日買い物に行き、友達に会いました。
最近オープンしたスーパーの話を聞いて、早速行ってみました。
セールをやっていて、野菜を安く買うことができました。
接続詞で論理をつなぐ
接続詞を使うことで文章の流れをイメージしやすくなります。
読む側がイメージできることは、「読みやすい」と感じることに大きく影響します。
記事を書き始めた。途中で詰まった。書くのをやめた。
記事を書き始めたのですが、途中で手が止まってしまいました。
結局、今日は書くのをやめることにしました。
主語と述語を近づける
主語と述語が離れていると、どことどこが繋がっているのか考える手間が発生して
読みにくくなります。主語と述語はなるべく近くに書く。
私が子どものころ雨の日が大好きだった理由は、長靴をはいて傘をさすことが特別な感じがしてワクワクする思い出がたくさんあったからです。
私は子どものころ、雨の日が好きでした。 長靴を履いて、傘をさすのが特別に感じたからです。
難しい言葉はやさしく言い換える
難しいことばは、離脱の原因になります。
中学生でもわかることばで書くことがおすすめ。
サブスクリプション型の収益モデルを採用しています。
月額制のサービスを使っています。
読点でリズムを整える
読点は音読したときに自然に息継ぎしたくなる場所に、入れるのがコツです。
文章のリズムが整うと、スラスラ読めると感じてもらいやすくなります。
ブログを書きたいけれど文章が苦手でなかなか進みません。
ブログを書きたいけれど、文章が苦手で、なかなか進みません。
箇条書きを活用する
一文の中に情報を詰め込むより、箇条書きを使うと頭の中でも整理されて読みやすくなります。
特に「〜と〜と」のような並列が続く場合は、箇条書きで視覚的に区切るのがベスト。
今週忘れずにやらなければいけないことは、書類を送付することと、冬服をクリーニングに出すことと、来月の休み希望日を上司に伝えることです。
今週のTo Doリスト:
・書類を送付する
・冬服をクリーニングに出す
・来月の休み希望日を上司に伝える
音読してチェックする
書いたあとに音読すると、「ん?」と引っかかる場所に気づけます。
黙読でもOKなので、音読してチェックをすることを忘れずに。
3ステップで実践!読みやすい文章に変える

STEP1:自分の文章をチェックする
まずは、書いた文章をチェックリストで確認して、具体的な改善点を見つけましょう!
| No | チェックポイント | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1つの文に、いろいろなことを詰めこみすぎていない? | ||
| 2 | 誰に向けて書いているか、はっきりわかる? | ||
| 3 | 話の順番はスムーズ?(結論→理由→具体例など) | ||
| 4 | 1文が長すぎていない?(だいたい60文字以内) | ||
| 5 | 「だから」「でも」「たとえば」などで話をつないでいる? | ||
| 6 | 「誰がどうした」がすぐにわかる?(主語と動きが近い?) | ||
| 7 | カタカナやむずかしい言葉を、わかりやすい言葉に直している? | ||
| 8 | 読点(、)を入れて、読みやすいリズムになっている? | ||
| 9 | 箇条書きを使って、スッキリ見せているところがある? | ||
| 10 | 最後に声に出して読んでみて、つっかえずに読めた? |
できてない箇所がいくつもあると、落ち込まなくて大丈夫です!
まずは改善点を見つけるということが大きな一歩です。
STEP2:構成の型を知る
初心者でも使いやすい「2つの型」を紹介します。
この型を使うだけで、文章にまとまりが出て、グッとわかりやすくなります。
まずは、それぞれの型を理解するところから始めましょう。
列挙型
読みやすく・整理された文章の黄金パターン
- 【全体像(導入)】
◯◯には、主に3つのポイントがあります。 - 【列挙1】
1つ目は◯◯です。〜(説明)←PREP型を使う - 【列挙2】
2つ目は◯◯です。〜(説明) - 【列挙3】
3つ目は◯◯です。〜(説明) - 【まとめ】
以上の3点を意識することで、◯◯が改善されやすくなります。
最初に「いくつポイントがあるか」を伝えることで、読む側は内容を整理しながら
理解しやすくなります。
PREP型
説明をするときに使う型です。
結論→理由→具体例→結論の順で書く
- P(結論):私は◯◯だと思います。
- R(理由):なぜなら◯◯だからです。
- E(具体例):たとえば、◯◯という経験があります。
- P(まとめ):だから◯◯なのです。
読み手が自然に納得できる流れを作り、説得力が高まります。
日常から「結論から言うと」を癖づけるように、使う場面を増やして練習しています。
STEP3:構成の型を繰り返して慣れる
まずは、上記で紹介した2つの型のテンプレートを使って、
短い文章をたくさん考えてみましょう。
型に慣れることで、自然と読みやすい文章が書けるようになります。
- ブログを書くとき
- クライアントに報告をするとき
- LINEでメッセージを送るとき
どんな場面でも「型を意識して書く」ことを練習してみてください。
また、日常会話でも「結論から言うと~」を口ぐせにして、
使う機会をどんどん増やしていきましょう。
型を意識して数をこなすうちに、わかりやすい文章が書けるようになります。
まとめ:文章はセンスではなく、型と練習で上達する
読みやすい文章は、もともとのセンスではありません。
「コツを知る」→「型を使う」→「数をこなす」
このシンプルな流れを繰り返すことで、誰でも確実に上達していきます。
まずは今日、1つでもこれならできそうと思ったポイントを意識して、
書いてみてください。
最初は小さな変化でも大丈夫です。
それが積み重なると、だんだん上達します。
私も、毎日少しずつ練習を重ねています。
一緒に伝わる文章力を育てていきましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。